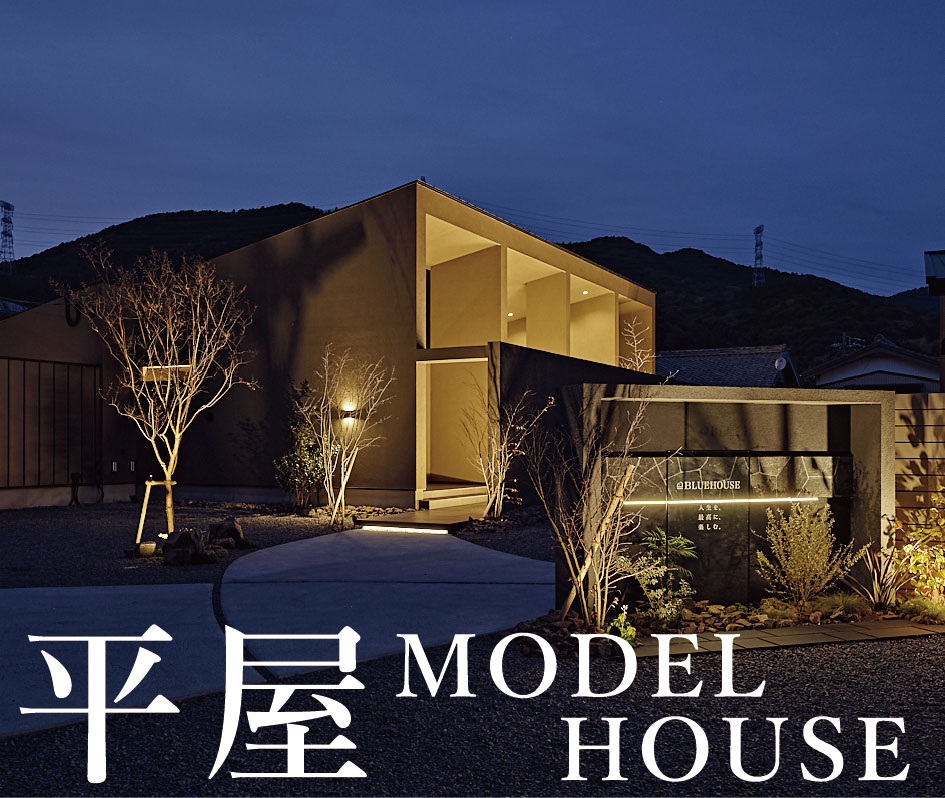「高気密住宅はカビが発生しやすい」は誤解|カビが発生する要因や換気方法、湿度が高いときの対処法を解説

「高気密住宅はカビが発生しやすい」と耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
しかし、この認識は正確ではありません。
高気密住宅は、適切な換気と湿度管理が行われていれば、むしろカビは発生しにくいです。
この記事では、高気密住宅の特徴とカビが発生する要因、効果的な換気方法、湿度対策を分かりやすく解説します。
快適な暮らしを実現するヒントがあるので、ぜひごらんください。
<コラムのポイント>
- ・高気密住宅は、気密性・断熱性が高く、カビが発生しにくい住宅です。
- ・換気が不十分であったり、結露を放置したりしているとカビが発生する可能性があります。
- ・適切な換気や除湿を行うことで、カビの発生を防ぐことができ、快適に暮らせます。
目次
高気密住宅とは

高気密住宅とは、建物にすき間が少なく、外気の影響を最小限に抑えられる住宅のことです。
住宅の気密性能は、C値という数値で示すことができ、一般的にC値1.0以下を高気密住宅とすることが多いです。
C値が小さいほど、住宅の気密性能が高いことを示しています。
高気密住宅は、高い断熱性能も備えており、エネルギー効率が良い点も特徴です。
ブルーハウスでは、全棟気密測定を行なっています。
ブルーハウスの2021年完工新築物件の平均C値は0.3と高い気密性を実現してます。
<あわせて読みたい>
C値の目安やC値を確認する気密測定の方法は、以下のコラムでも解説していますので、あわせてお読みください。
「高気密住宅はカビが発生しやすい」は誤解

高気密住宅に対して「カビが発生しやすい」というイメージを持つ方がいらっしゃいますが、これは誤解です。
高気密住宅は、結露が起きにくい構造のため、カビは発生しにくいです。
しかし、換気が不十分だと室内に湿気がたまり、カビの原因となる場合があります。
高気密住宅を選ぶ際には、適切な換気設備と湿度管理方法を取り入れることが大切です。
高気密住宅の特徴や基準、メリット・デメリットは、以下のコラムでも解説していますので、あわせてお読みください。
<あわせて読みたい>
カビが発生しやすい条件

高気密住宅のカビ対策を考える前に、まずカビがどのような条件で発生しやすいのかを解説します。
カビが発生しやすい条件は、以下のとおりです。
- ・湿度が60%以上
- ・温度が20℃〜30℃
- ・カビの栄養源がある
湿度が60%以上
湿度が60%以上になると、カビが繁殖しやすくなります。
高気密住宅では室内の空気が外に逃げにくいため、適切な換気を行わないと室内湿度が上昇しやすくなります。
湿度が高いときには換気や除湿を行い、湿度を60%未満に保つことが重要です。
温度が20℃〜30℃
カビが最も活発に繁殖する温度帯は20℃〜30℃です。
梅雨の時期などは湿度も高く、外気温もカビが繁殖しやすい温度帯のため、注意が必要です。
カビの栄養源がある
カビは有機物を栄養源として繁殖します。
代表的なカビの栄養源は、ほこりや食べ物のかす、皮脂や垢などです。
家具の裏側や押入れ、クローゼットなどは、ほこりが溜まりやすいため、注意が必要です。
定期的に掃除を行うことや家具の配置を工夫して空気の流れを作ることで、カビの発生を抑えることができます。
高気密住宅でカビの発生要因となる表面結露と内部結露

高気密住宅で、注意すべきものに結露があります。
適切な換気と湿度管理が行われていれば、結露は発生しにくいですが、対策が不十分だと結露が発生します。
結露には、表面結露と内部結露の2種類があります。
結露の放置は、カビの発生要因となるだけでなく、建物の劣化や腐食を進行させる要因となるため、注意が必要です。
表面結露とは
表面結露とは、室内の暖かく湿った空気が、冷えた窓ガラスや壁などの表面に触れて水滴になる現象のことです。
水滴がたまると窓周りや壁紙にカビが発生します。
表面結露は、目に見えるため、放置せず、その都度、拭き取りましょう。
内部結露とは
内部結露とは、壁の中や天井裏など、見えない構造部分で起きる結露です。
室内の湿気が壁内に侵入し、断熱材の内部などで冷やされて水滴になります。
内部結露は、カビを発生させるだけでなく、建物の劣化や腐食を進行させる要因となります。
目に見えない場所で発生し、水滴を拭き取ることもできないため、換気を行い、内部結露を発生させないことが重要です。
高気密住宅でカビが発生しやすい場所

高気密住宅では、適切な換気が行われていないと、カビが発生しやすい場所があります。
高気密住宅で、カビが発生しやすい場所は、以下のとおりです。
- ・浴室や洗面所などの水回り
- ・窓周辺
- ・壁の中や天井裏
- ・クローゼット内
- ・床下
浴室や洗面所などの水回り
浴室や洗面所などの水回りは、常に湿気が多くカビが発生しやすい場所です。
入浴後は、換気扇を回し、浴室の扉を閉め、居室内に湿気が流入しないようにしましょう。
浴室に窓が設置されているご家庭は、窓を開け、外に湿気を逃がすことも有効です。
壁や床の水滴を拭き取ることや、排水溝の掃除を行うことを入浴後の習慣にすると、カビの発生を防ぐことができます。
窓周辺
窓は外気との温度差で表面結露が発生しやすく、特にサッシ部分は、水滴がたまりやすので、カビが発生することがあります。
高気密住宅は、結露が発生しにくい住宅ですが、気密性や換気が不十分だと、結露が発生することがあります。
表面結露は放置せず、こまめに水滴を拭き取ることが重要です。
壁の中や天井裏

壁の中や天井裏には、グラスウールなどの断熱材が使用されていますが、断熱材が湿気を含むと、内部結露が発生し、カビが繁殖することがあります。
内部結露は、建物の劣化や腐食を進める要因にもなるため、注意が必要です。
施工段階で防湿シートを適切に設置することや、適切な換気設備を備えることで、カビの発生を抑制できます。
クローゼット内
クローゼット内は通気性が悪く、湿気がたまりやすいため、カビが発生しやすくなります。
衣類や物品を詰め込みすぎないようにし、定期的に扉を開けて空気を循環させましょう。
除湿剤を設置することも有効です。
床下
床下は湿気がたまりやすく、空気が循環しにくい場所です。
床下換気口の確保や換気扇を設置することで、湿気を抑えてカビの発生を防ぐことができます。
高気密住宅のカビ対策

高気密住宅は高い気密性と断熱性を持ち、快適な暮らしを実現できますが、適切なカビ対策は意識しておくことが重要です。
高気密住宅のカビ対策は、以下のとおりです。
- ・換気を行う
- ・結露を放置しない
- ・清潔に保つ
換気を行う
高気密住宅において最も重要なカビ対策は、適切な換気を行うことです。
高気密住宅では、空気が滞留するため、意識的に換気を行わないと、カビが発生する可能性があります。
換気システムを利用し、室内の湿った空気を外に排出して新鮮な空気を取り入れることが大切です。
特に湿度が高くなりやすい浴室やキッチンなどの水回りでは、換気扇を使用して積極的に換気を行いましょう。
結露を放置しない
結露はカビが発生する原因となるため、こまめな対応が必要です。
特に冬場は窓ガラスやサッシ部分に表面結露が起こりやすくなります。
表面結露が発生したら早めに拭き取り、湿気が室内に残らないようにしましょう。
結露防止シートを使用したり、断熱性能の高い窓を採用したりすることで、結露そのものを防ぐこともカビ予防に効果的です。
清潔に保つ
カビはほこりや汚れを栄養源として繁殖するため、住宅内を清潔に保つことが大切です。
特にほこりがたまりやすい家具の裏側や収納スペース、壁際などは定期的に掃除をしましょう。
高気密住宅の換気方法

2003年以降に建築された住宅では、法律で24時間換気システムの設置が義務化されています。
24時間換気システムは、カビの発生を防ぐために不可欠な設備です。
24時間換気システムは、以下の3種類に分類されます。
- ・第1種換気システム
- ・第2種換気システム
- ・第3種換気システム
住宅では、第1種換気システムと第3種換気システムが採用されることが多いです。
それぞれ、メリット・デメリットがあるため、ご自身の生活に合った換気システムを選びましょう。
第1種換気システム
第1種換気システムは、機械による給気と排気を両方行う換気方法です。
室内に新鮮な空気を積極的に取り入れると同時に、汚れた空気を強制的に排出するため、空気の循環効率が高くなります。
高気密住宅では、温度や湿度を一定に保ちやすいため、熱交換型の第1種換気システムが多く採用されています。
熱交換型換気システムとは、室内から排出される空気の熱を再利用して、外から取り入れる空気の温度を調整するシステムです。
エネルギー効率がよく、室内の温度や湿度のバランスを安定させ、カビの予防に効果的です。
【第1種換気システムのメリット】
- ・熱交換機能により省エネルギー
- ・室内の湿度や温度を一定に保ちやすい
- ・安定的に換気できる
【第1種換気システムのデメリット】
- ・設備費用が高め
- ・定期的なメンテナンスが必要
第2種換気システム
第2種換気システムは、機械で給気を行い、自然に排気を行う換気方法です。
室内に新鮮な空気を送り込み、室内の圧力を高くすることで、自然に排気されます。
病院やクリーンルームなどで採用されることが多く、一般的な住宅ではあまり使用されません。
【第2種換気システムのメリット】
- ・特殊な空間での使用に適している
【第2種換気システムのデメリット】
- ・一般住宅では採用しにくい
第3種換気システム
第3種換気システムは、機械で室内の空気を強制的に排出し、外気は自然に取り入れる換気方法です。
設置コストが安く、住宅で最も広く採用されています。
室内の空気を積極的に排出するため、湿気を効率よく除去し、カビの発生を抑える効果があります。
【第3種換気システムのメリット】
- ・設置費用が安価で導入しやすい
- ・室内の湿気を効果的に排出できる
- ・メンテナンスが比較的容易
【第3種換気システムのデメリット】
- ・冬季は外気の影響で室温が下がりやすい
- ・外気の汚染物質が侵入する可能性がある
24時間換気システムについては、以下のコラムでも解説していますので、あわせてお読みください。
高気密住宅で湿度が高いときの対処法

高気密住宅では、適切に換気をしていれば、そこまで湿度が高くなることはありません。
しかし、梅雨の時期や室内干しをした際などは、湿度が上がりやすいため、以下の方法で、対処していきましょう。
- ・エアコンの除湿機能を活用する
- ・除湿機を使う
- ・除湿剤を使う
エアコンの除湿機能を活用する
高気密住宅の湿度対策として手軽で効果的なのは、エアコンの除湿機能を使うことです。
エアコンの除湿機能を使えば、室内の湿気を効率よく除去できます。
梅雨の時期や室内干しをした際は、積極的にエアコンの除湿モードを活用しましょう。
除湿機を使う
洗面所やランドリールームなど、湿度が高くなりやすい場所では、除湿機の使用が効果的です。
除湿機はエアコンと違い、持ち運びができるため、1台あると便利です。
衣類乾燥機能が付いているタイプは、室内干しをするご家庭で重宝されています。
除湿剤を使う
クローゼットや押し入れ、靴箱など、換気がしにくい場所では市販の除湿剤がおすすめです。
住宅全体の換気をしても、小さな収納空間に湿気がたまっているケースはあります。
エアコンや除湿機と比べ、除湿効果は限定的ですが、上手に活用しましょう。
新築で高気密住宅を建てる際のポイント

新築で高気密住宅を建てる際は、気をつけるべきポイントがあります。
理想のマイホームを完成させるために、以下の点を確認しましょう。
- ・気密測定の数値を確認する
- ・結露しにくい窓を選ぶ
- ・実績のある施工業者を選ぶ
気密測定の数値を確認する
気密測定とは、住宅にどれほどのすき間があるかを数値で確認する作業です。
高気密住宅とあっても、気密性にはばらつきがあります。
気密性は、C値と呼ばれる指標で数値化され、一般的にはC値が1.0以下であれば気密性が高いとされています。
新築で高気密住宅を建てる際は、気密測定の数値を確認しましょう。
施工業者を選ぶ際は、定期的な気密測定ではなく、全棟気密測定を行っている業者を選ぶと安心です。
ブルーハウスでは全棟気密測定を行っており、2021年完工新築物件の平均C値は0.3でした。
<あわせて読みたい>
結露しにくい窓を選ぶ
カビ予防の観点からいえば、結露しにくい窓を選ぶことも重要です。
結露しにくい樹脂窓を標準仕様としている施工業者もあるため、仕様を確認しておくと安心です。
実績のある施工業者を選ぶ
高気密住宅の性能を最大限に引き出すためには、実績のある施工業者の選定が重要です。
高気密・高断熱住宅は、通常の住宅とは異なる施工技術が求められ、大工の腕と丁寧さが気密性能に直結します。
過去の施工例や気密測定の数値などを確認した上で、安心して任せられる施工業者を選びましょう。
まとめ
今回は、高気密住宅とカビの関係、カビの発生要因や換気方法、湿度が高いときの対処法などを解説しました。
高気密住宅は、気密性・断熱性が高く、カビが発生しにくい住宅です。
適切な換気や除湿を行うことで、カビの発生を防ぐことができ、快適に暮らすことができます。
本コラムが高気密住宅を検討中の方の参考になれば幸いです。
ブルーハウスは、豊橋市でオーダーメイドのデザインと快適性、住みやすさを両立した家づくりをしています。
- ・デザインも性能も叶えて、長く快適に経済負担の少なく住める家をつくっています。
- ・ブルーハウスは、高気密高断熱住宅にこだわっています。(現在HEAT20G2グレードを中心に建築。全棟気密測定(C値測定)を実施)
- ・無垢材や塗り壁など、自然の素材を使った家づくりが得意です。
- ・土地探しからも始められて、建てたい家や住みたい地域、住みたい環境から適した土地をお探しします。
愛知に住む人、豊橋に住む人を家づくりで幸せにする。「人生を最高に楽しむ家」をつくることを目指して家づくりをしています。
豊川で暮らしを楽しむ!豊川モデルハウスで体感ください
ブルーハウスは2024年、豊川市に豊川モデルハウスをオープンしました。ブルーハウスの家づくりをもっと知りたい方、住み心地を体感したい方、デザインを詳しく見てみたい方は、ぜひお気軽にご来場ください。







 平屋は軒あり、軒なしどちらがよいのか|900、1800mmなど軒の長さによるメリット・デメリットも解説
平屋は軒あり、軒なしどちらがよいのか|900、1800mmなど軒の長さによるメリット・デメリットも解説  二階建て平屋とは|二階建て平屋の間取り実例、メリット・デメリットを紹介
二階建て平屋とは|二階建て平屋の間取り実例、メリット・デメリットを紹介