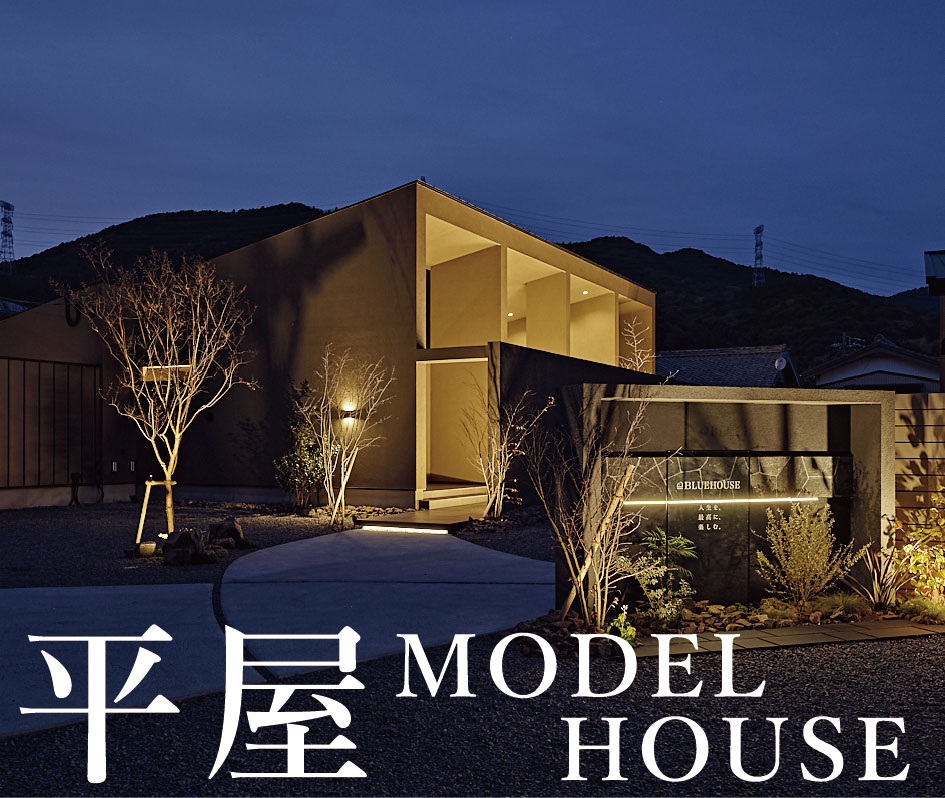気密性の高い家のデメリット・注意点と快適に住むための対策|C値の目安や気密性を上げる方法も解説

「気密性の高い家のメリットだけでなくデメリットも知りたい」
「気密性の高い家ならではの快適な住まい方のコツを知りたい」
このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。
そこでこのコラムでは、全棟気密測定を実施し、高気密住宅を実現している愛知の工務店『ブルーハウス』が、以下について解説します。
<コラムのポイント>
-
気密性の高い家のメリット・デメリットやC値の目安などを分かりやすく解説します。
-
高気密住宅のデメリットや注意点を対策して、快適に住まう方法をチェックしましょう。
-
気密性の高い家を建てるコツやハウスメーカーの選び方も紹介します。
高気密・高断熱で1年中快適・省エネな住まいを実現するために参考にしてください。
目次
気密性が高い家とは?

気密性とは、家全体で「隙間が少ない」ことを表す性能です。
気密性が高い家とは、できるだけ隙間をつくらないように建てられた家のことです。
住宅の気密性能は、C値(相当隙間面積)という、家の延べ床面積に対して隙間面積がどれだけあるかの割合で示される値で示されます。
C値=家の隙間面積(㎠)/建物の延べ床面積(㎡)
<合わせて読みたい>
気密性の高い家のメリット

気密性の高い家には、以下のようなさまざまなメリットがあります。
省エネ性能が高まる
気密性の高い家は、室内⇔屋外の空気(熱)の出入りが少ないため、外気の影響を受けずに室温をキープしやすくなり、冷暖房効率がアップして光熱費を抑えることにつながります。
室内の快適性を向上させる
気密性の高い家は、隙間から入ってくる風によって室温にムラができることを防ぎ、快適性が向上します。
また、家の中でも場所によって寒すぎたり暑すぎたりすることがないため、ヒートショックなどの事故を予防することにもつながります。
家を劣化しにくくする
気密性の高い家は壁体内への湿気の流入を抑えられるため、躯体内の結露(内部結露)の発生を防いで建物を劣化しにくくすることにもつながります。
内部結露が続くと柱や土台が傷み、耐震性や耐久性が損なわれる可能性があります。
高い気密性があれば、室内の湿気が壁の中に流れ込む心配はなくなり、住宅の老朽化を進ませずにすみます。
遮音性能が高まる
気密性を高めると、空気を伝ってくる音の出入りをシャットアウトできるため、遮音性が向上します。
住宅のすき間からの音漏れや外部の音の侵入を軽減できるため、ストレスも少なくなります。
計画的な換気の効率を高める
家の気密性を高めることで、換気経路を明確にして、計画換気を効率的に行える点もメリットです。
逆に、家の中に意図しない隙間が多い(気密性が低い)と、24時間換気システムで計画した空気の流れが上手くいかない原因になります。
花粉やウイルス、汚染物質の侵入を防ぐ
気密性が高い家は、外気に含まれる花粉や黄砂やPM2.5など、健康を害する有害物質の流入を抑えられます。
換気扇の給気口に適切なフィルターを設置することで、24時間新鮮で綺麗な空気を維持できるため、健康にも配慮した暮らしができます。
気密性の高い家のデメリット・注意点と対策

気密性の高い家づくりを検討する際に知っておきたい、デメリットや注意点を対策とセットで紹介します。
気密性が高いからこその注意点や住まい方のコツを知っておくことで、長く快適に住み続けることができますので、参考にしてください。
室内が乾燥しやすい
気密性の高い家は、室内の湿気が高くなりやすい梅雨の期間でもエアコンの運転によって湿度を抑えられます。
一方で、地域によっては冬場などに室内が乾燥しやすくなるという注意点があります。
冬の湿度が低い地域では、エアコンで室内の空気を暖めることでさらに乾燥しやすくなるため、気になる場合は以下のような対策をしましょう。
〈対策例〉
- ・必要に応じて加湿器を使う
- ・加湿機能のあるエアコンを取り入れる
- ・室内に調湿性のある建材(漆喰など)を採用する
- ・室内干しをする
- ・観葉植物を置く など
石油ストーブなどの暖房器具に注意
気密性の高い家では、ファンヒーターや石油ストーブといった家の中で火を燃焼させて暖める暖房器具は酸欠の恐れがあります。
使用の際には以下の点を意識しましょう。
〈対策例〉
- 使用時は窓を開けて換気をする
- 特に寒い日の夜など短時間に限定して運転し、換気の風量を強める など
排気用の煙突がついたファンヒーターや薪ストーブは使うことができます。
換気システムを適切に運用する必要がある
現在の住宅には24時間換気システムの設置が義務付けられています。
気密性の高い家で換気システムを長時間切ると、室内の空気の流れが悪くなり、結果として結露が出やすい、ニオイが残る、ホコリがたまりやすいなどの不快な空気環境になることがあります。
室内の湿度を調節したい場合は加湿器や除湿機を使うようにし、換気システムを24時間稼働させることで快適な空気環境を保ちやすくなります。
気密性の高い家や高断熱住宅のメリット・デメリットは、以下のコラムでも詳しく解説していますので、合わせてお読みください。
家の気密性(C値)はどれくらいあればいい?数値の基準や目安
家の気密性を示す数値(C値)は、高気密高断熱住宅なら1.0㎠/㎡以下、24時間換気システム(第1種、第3種)の能力を発揮させるためには0.7㎠/㎡以下が望ましいとされています。
C値を確認する気密測定の方法

「気密測定」とは住宅の隙間の面積を専用の機械(気密測定器)を使って計算する検査のことです。
気密測定器による検査の流れは以下の通りです。
- ①送風機などの機器を窓辺に設置する
- ②住宅のすべての換気口を養生テープで塞ぐ(目張り)
- ③測定器を設置する窓部分の目張り
- ④気密測定器を設置する
- ⑤屋外の風力を確認する
- ⑥窓やドアの施錠確認
- ⑦気密測定しC値を算出する
気密測定は、建物が完成してから実施する場合と、断熱気密工事が完了した時点で測定(中間測定)する場合があります。
中間測定を実施すれば、その時点での隙間の量と正確な位置が特定できるため、さらに気密性能を高める工夫もできます。
ブルーハウスでは、施工するすべての家に対して気密測定を実施しています。2021年完工の新築物件の平均でC値は0.3㎠/㎡と、高い気密性を実現しています。
家の気密性を上げる方法

注文住宅の新築時に、気密性を高めて快適な住まいを実現するためのポイントを紹介します。
気密工事を確実に行う
住宅の気密性を高めるには、隙間ができない施工(気密工事)が重要です。
特に、壁と壁、壁と柱、柱と梁、壁と配管・スイッチ・コンセントなど、異なる部材や構造体が隣接し合う部分の隙間をなくし、空気が出入りしにくいようにするための丁寧な施工が求められます。
気密化しやすい構造の窓を選ぶ
例えば、滑り出し窓やFIX窓は引き違い窓よりも気密性が高いので、採光のみに使う場所など、使用目的や場所に応じて窓の種類を使い分けるのも有効です。
全棟気密測定を実施、C値の実績がある工務店・ハウスメーカーを選ぶ
気密性の高い家づくりを依頼するなら、全棟気密測定を実施し、平均的に高い気密性を確保している工務店やハウスメーカーを選ぶのがおすすめです。
例え高性能な建材を採用しても、しっかりと気密工事が実施されていなければ、気密性は向上しません。
実際の施工物件でC値を毎回測定し、平均的に良い数値を出している工務店やハウスメーカーなら、職人の施工力が高く信頼できると判断できます。
まとめ
気密性が高い家は、省エネ性能向上、室内の快適性向上、家の劣化防止、遮音性能向上、計画換気の効率化、花粉や汚染物質の侵入防止などのメリットがあります。
一方、乾燥対策や暖房器具の選択、換気システムの適切な運用など、高気密住宅の特徴を理解した上で快適に住むための工夫も重要になります。
気密性の高い家を建てるなら、適切な断熱気密工事を実施し、C値を全棟で実測した上で高気密の実績がある工務店やハウスメーカーを選ぶことがポイントです。
ブルーハウスでは、「高断熱と高気密はセットである」と考え、施工するすべての家に対して気密測定を実施しています。2021年完工の新築物件の平均でC値は0.3㎠/㎡と、高い気密性を実現しています。
愛知県、豊橋・豊川エリアで高気密・高断熱な家づくりを検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
豊川で暮らしを楽しむ!豊川モデルハウスで体感ください
ブルーハウスは2024年、豊川市に豊川モデルハウスをオープンしました。ブルーハウスの家づくりをもっと知りたい方、住み心地を体感したい方、デザインを詳しく見てみたい方は、ぜひお気軽にご来場ください。





 断熱等級6とは?等級5・7との仕様・UA値・光熱費の違いや使える補助金、快適な住まいを叶えるハウスメーカーの選び方を紹介
断熱等級6とは?等級5・7との仕様・UA値・光熱費の違いや使える補助金、快適な住まいを叶えるハウスメーカーの選び方を紹介  パッシブデザイン建築の魅力とは|注文住宅で心地よく暮らすための設計ポイントを解説
パッシブデザイン建築の魅力とは|注文住宅で心地よく暮らすための設計ポイントを解説